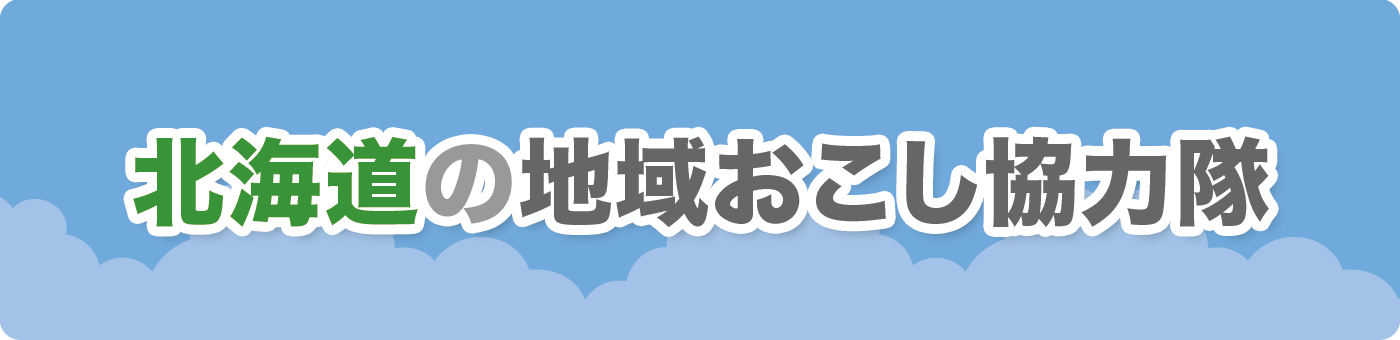 子どもと地域・学校をつなぐ、下川町の「共育」をミッションに。
子どもと地域・学校をつなぐ、下川町の「共育」をミッションに。
2022年11月7日 公開
子どもの未来にまつわる最多のパブリックコメント。
下川町は木質バイオマスボイラーによってエネルギーの自給を進め、コストダウンした分の予算で子育て支援を手厚くすることなどにより、移住者の数も増加傾向です。ただ、現在の人口減は緩やかですが、2030年には人口は2000人台に落ち込むことが予測されています。
その2030年までに私たちに何ができるのか、ふるさとのありたい姿はどんなものか、町民と役場職員で構成される部会を立ち上げ議論を重ねました。話し合いも終盤に差し掛かり、目標6つをベースとした「2030年における下川町のありたい姿(案)」を事務局が作成し、パブリックコメントに図ることを会議で確認したところ、委員からは「子どもたちの未来」についても目標に入れてほしいとの意見があがりました。話し合いの結果「子どもたちの笑顔と未来世代の幸せを育むまち」を追加し、目標を7つに設定してパブリックコメントを実施したところ、町政史上最多の118件も意見が寄せられました。その中でも「子どもたちの笑顔と未来世代の幸せを育むまち」についての意見が全体の30%を占めており、興味関心がある方が数多いことが分かりました。
その後、「子どもたちの未来」の部分についてもっと考えていくため、地域で子どもを取り巻く環境をどう作っていくかのビジョンとして「地域共育ビジョン」の作成に取り組みました。子どもを取り巻く環境は「学校」「家庭」「地域」の3つの要素からなるため、それぞれの領域から計16名が集まり、地域共育ビジョンの策定に向けて話し合いが行われ、2020年に地域共育ビジョンが策定されました。
私は、地域おこし協力隊として下川町に赴任し、どのようにビジョン策定を行っていくかや、会議やビジョン策定のプロセス設計や運営などを担いました。
その2030年までに私たちに何ができるのか、ふるさとのありたい姿はどんなものか、町民と役場職員で構成される部会を立ち上げ議論を重ねました。話し合いも終盤に差し掛かり、目標6つをベースとした「2030年における下川町のありたい姿(案)」を事務局が作成し、パブリックコメントに図ることを会議で確認したところ、委員からは「子どもたちの未来」についても目標に入れてほしいとの意見があがりました。話し合いの結果「子どもたちの笑顔と未来世代の幸せを育むまち」を追加し、目標を7つに設定してパブリックコメントを実施したところ、町政史上最多の118件も意見が寄せられました。その中でも「子どもたちの笑顔と未来世代の幸せを育むまち」についての意見が全体の30%を占めており、興味関心がある方が数多いことが分かりました。
その後、「子どもたちの未来」の部分についてもっと考えていくため、地域で子どもを取り巻く環境をどう作っていくかのビジョンとして「地域共育ビジョン」の作成に取り組みました。子どもを取り巻く環境は「学校」「家庭」「地域」の3つの要素からなるため、それぞれの領域から計16名が集まり、地域共育ビジョンの策定に向けて話し合いが行われ、2020年に地域共育ビジョンが策定されました。
私は、地域おこし協力隊として下川町に赴任し、どのようにビジョン策定を行っていくかや、会議やビジョン策定のプロセス設計や運営などを担いました。
一人ひとりの「やりたい」を形にする高校の課題研究授業。
地域共育ビジョンのもと、学校教育、社会教育両面から数多くの取り組みを行ってきました。学校教育では、総合的な学習の時間等で、地域の情報や人をつないでいます。
中でも、下川商業高校の3年生を対象とした課題研究授業は、多くの町の人とのかかわりがある授業です。高校としても、いま求められている「探究」の力を伸ばすために、授業内容を毎年工夫しています。以前はグループで決められた課題の中から選ぶスタイルだったものを、個人の「好きなこと」「得意なこと」「求められていること」を深堀りしてテーマ設定する形に変わりました。地域で活動しているゲストから取り組みを聞き、また自分のテーマについて聞いてもらうことで、自分を活かしながら地域のためになるプロジェクトになるように模索をしていきます。
過去のプロジェクトには廃材を使ったフォトフレームづくり、町内飲食店のデリバリーサービス、模擬ウエディングに、SDGsをテーマにした子どもたちの公園スタンプラリーなどがあり、授業を通して「町内の魅力を再発見した」「大人がこんなに協力してくれると思わなかった」といった感想を聞くことができたのが印象的でした。
中でも、下川商業高校の3年生を対象とした課題研究授業は、多くの町の人とのかかわりがある授業です。高校としても、いま求められている「探究」の力を伸ばすために、授業内容を毎年工夫しています。以前はグループで決められた課題の中から選ぶスタイルだったものを、個人の「好きなこと」「得意なこと」「求められていること」を深堀りしてテーマ設定する形に変わりました。地域で活動しているゲストから取り組みを聞き、また自分のテーマについて聞いてもらうことで、自分を活かしながら地域のためになるプロジェクトになるように模索をしていきます。
過去のプロジェクトには廃材を使ったフォトフレームづくり、町内飲食店のデリバリーサービス、模擬ウエディングに、SDGsをテーマにした子どもたちの公園スタンプラリーなどがあり、授業を通して「町内の魅力を再発見した」「大人がこんなに協力してくれると思わなかった」といった感想を聞くことができたのが印象的でした。
子どもたちの思いが地域に見え、応援する大人を増やす!
2021年には、「地域共育ビジョン」の中の「子どものわくわくする好奇心と挑戦を育む地域」、「子どもたちがほっとする居場所がたくさんある地域」に紐づく、10代が集まれる場所として空き店舗を活用した期間限定の10代スペースKOTOBUKI」を実施しました。下川町では学校の部活数が限られ自分が本当にやりたいことに挑戦する機会が持ちにくい現状もあることから、いろんな大人と出会って見識を広げることで将来の可能性を広げる場としても活用してもらえればと思いました。
卓球台を置いて学年の壁を超えて遊べるように工夫したり、ダーツを大人も子どもも楽しんだり、良い交流の場として機能したと思います。町内の編み物が好きな方などに作品を提供してもらい、子どもが「ありがとう」のメッセージを送ることでプレゼントしてもらえる「おゆずりコーナー」も好評。子どもたちも「大人とふれ合えるのが新鮮」「コロナ禍で他学年と遊べなかったけれど、ここに来ると誰かと会える」と言ってくれました。
現在、教育委員会の職員(地域学校協働コーディネーター)として、他にも中学校の職場体験や小中高校が連携した総合学習の時間を組むなど、多彩な取り組みにチャレンジしています。地域おこし協力隊メンバーをはじめ、地域学校協働推進委員やキッズスクールコーディネーターなどと共に、子どもたちの思いが地域に可視化され、応援する大人の数を増やすことで、皆で「共育」を後押しできる地域を作っていきたいです。
卓球台を置いて学年の壁を超えて遊べるように工夫したり、ダーツを大人も子どもも楽しんだり、良い交流の場として機能したと思います。町内の編み物が好きな方などに作品を提供してもらい、子どもが「ありがとう」のメッセージを送ることでプレゼントしてもらえる「おゆずりコーナー」も好評。子どもたちも「大人とふれ合えるのが新鮮」「コロナ禍で他学年と遊べなかったけれど、ここに来ると誰かと会える」と言ってくれました。
現在、教育委員会の職員(地域学校協働コーディネーター)として、他にも中学校の職場体験や小中高校が連携した総合学習の時間を組むなど、多彩な取り組みにチャレンジしています。地域おこし協力隊メンバーをはじめ、地域学校協働推進委員やキッズスクールコーディネーターなどと共に、子どもたちの思いが地域に可視化され、応援する大人の数を増やすことで、皆で「共育」を後押しできる地域を作っていきたいです。
まとめ:北海道下川町の地域おこし協力隊(地域共育コーディネーター)
◎下川町では地域共育コーディネーターを務める地域おこし協力隊を募集
◎下川町の「地域共育ビジョン」の実現に向けた取り組みを推進
◎学校と地域を結び、課題研究などの授業支援も実施
◎子どもの思いが見え、応援する大人が増える環境を目指す
◎最長3年まで任期を延長することが可能
◎下川町の「地域共育ビジョン」の実現に向けた取り組みを推進
◎学校と地域を結び、課題研究などの授業支援も実施
◎子どもの思いが見え、応援する大人が増える環境を目指す
◎最長3年まで任期を延長することが可能
北海道下川町教育委員会
北海道上川郡下川町幸町95番地
TEL.01655-4-02511
TEL.01655-4-02511
地域共育コーディネーターに関する情報・お問い合わせ
https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/2022/02/post-15.html
https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/2022/02/post-15.html
北海道の地域おこし協力隊
最新記事
「好き」「得意」を発揮して、上川町をプロデュース!
2023年5月29日 公開
食やコミュニティーづくりなど、地域おこし協力隊が各分野のプロデューサーとしてまちを盛り上げています。
子どもと地域・学校をつなぐ、下川町の「共育」をミッションに。
2022年11月7日 公開
「子どもたちの笑顔と未来世代の幸せを育むまち」の目標に向けた下川町の取り組みを紹介。
地域おこし協力隊で「起業」する!厚真町が育むローカルベンチャー。
2022年8月29日 公開
起業の意思を持った移住者が全国各地から集まってきている厚真町の取り組みを紹介。
北海道で「地域おこし協力隊」になるためには?活動事例や気をつけることは?
2022年7月27日 公開
地域おこし協力隊とは具体的にどんな活動をしているのか、なるためにはどうすればいいかなどを紹介。

