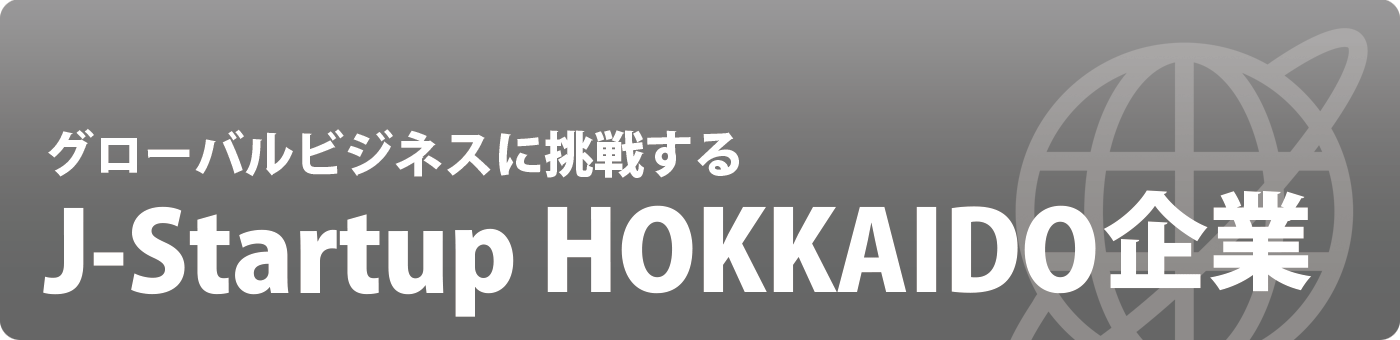 地域企業とともに、札幌をAI研究開発の集積地へ。【株式会社調和技研】
地域企業とともに、札幌をAI研究開発の集積地へ。【株式会社調和技研】
2022年10月21日 公開
AI技術を社会実装するための「接点」として創業。
「私はもともと大手ソフトウェア会社で人事や地域振興策の仕事に携わり、各地の大学を回っていました。調和系工学研究室とは特に親交が深く、先端的な研究成果を人の役に立てたいという言葉を常々聞いていたんです。私自身もベンチャーやAI技術の可能性に興味がありましたし、純粋に面白そうだと感じて参画しました」
とはいえ、当初はAIの意味を説明しようにも理解を得られず、社員が研究している技術を紐解くのも苦労の連続。「社員の給与を払うために私が商店街のイベントを企画したり、ティッシュ配りのバイトをして糊口をしのいだ時期もあります」と苦笑する。転機となったのは数年後に訪れたAIブーム。
「AIという言葉が広く知られたことをきっかけに、首都圏の企業から受託研究の業務が舞い込みました。当社は規模の小さな会社ではありながら、言語・画像・数値の3つの技術領域に対応でき、アカデミックなバックボーンを持つ専門性の高い社員が在籍しています。例えば、工場で良品と不良品を画像系AIで判別できるだけではなく、その先の効率化や出荷タイミングも数値系AI、言語系AIを用いて対応できるんです」
大学の研究室をベースにしたアカデミックなAI技術。それらを扱える高度な人材。他にはない強みによった依頼が次々に飛び込み事態は好転した。
「好き」を突き詰めるためのビジネスモデル。
「コロナ禍をきっかけに働き方はフルリモートにシフトしました。国内では東京だけではなく、京都や神戸、九州など各地で社員が働いていますし、外国人材は各国で活躍してもらっています」
ここ最近、中村さんが取り組んでいるのが組織の継続性を生み出すこと。これまでは大学の研究室の色合いが強かった一方、ビジネスとして強い体質へと成長するために多彩な業界から人材を受け入れ、管理部門の充実も図っている。
「AIエンジニアの人材不足は世界的な課題。なかなか人を増やせない状況で利益を高めるためにも、受託研究だけではないビジネスモデルが必要です。今後、新たに取り組もうと考えているのがライセンス事業。これまでのケーススタディをもとに、顧客の共通課題からAIエンジンを標準化し、いわゆるサブスクのようなスタイルで提供したいと考えています」
標準化されたAIエンジンに集積したデータを、今度は個別の受託研究に活用することで、開発スピードや生産性も高まる。利益と効率化を両立させる「ハーベストループ(勝ち続ける仕組みをつくるための戦略デザイン)」が目指すところだ。
「利益を手厚く、働く時間を少なくする真の意図は、社員が研究により力を割けるからです。当社の日常業務で大切にする価値観『バリュー』の中に『どうせなら、好きなことをとことん』があります。これは好きなこと、得意なことを率先して行い、自由と責任を両立させるという意味です。ライセンス事業を始めることで、仕事だけに人生を縛られないようにする時間がもっと生まれると思っています」
地元のAI人材を育成するための「札幌AI道場」。
「北大発のAIベンチャー企業として札幌に本社を置いているのだから、もっと地域経済に貢献して行くというのも当社の課題。そこでAI人材を育成するための実践的な学びの場『札幌AI道場』を、当社が旗振り役となり産学官連携で開くことにしました」
AI技術は座学だけでは十分なスキルを身につけられないため、地元IT企業の人材に実践的な開発経験を積んでもらうプログラム。課題を提供するのはコストや手法の不安からAI導入に踏み出せない地域の中小企業。参加IT企業はケーススタディを通じてAIを活用するためのスキルを高められ、課題提供企業は解決策の実用化を検討できるメリットがある。
「地元企業のAIやDXにまつわる案件を、地域のIT企業と一緒に解決することで潤いの輪を広げていくのが理想的。札幌をAI知識の集積地から、それを『活用できる人材の集積地』へと底上げしたいですね」
株式会社調和技研
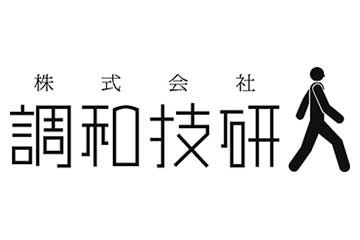
グローバルビジネスに挑戦するJ-Startup HOKKAIDO企業
最新記事5件
自らの経験を基に学生起業した千葉佳祐さんに、開発に至った経緯や苦労、今後のビジョンを伺った。
スマホアプリを中心に開発している株式会社インプルの代表、西嶋裕二さんに会社のビジョンを伺った。
灯油の自動発注・配送管理システム「GoNOW」の 開発と提供に取り組む、代表の多田満朗氏に話を伺った。
株式会社調和技研の代表取締役である中村拓哉さんに、これまでの歩みとこれから進んでいく方向についてインタビュー。
酪農・畜産を効率化するクラウド牛群管理システム「Farmnote Color」誕生の経緯や今後の展開について聞きました。




