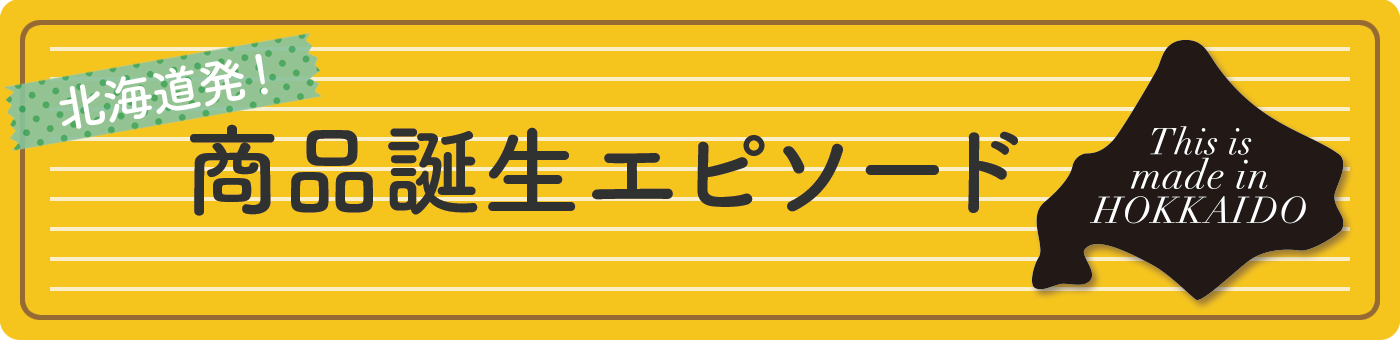 北海道発!商品誕生エピソード【骨までおいしいお魚。やわらか一夜干しにしん/有限会社丸イ伊藤商店(余市町)】
北海道発!商品誕生エピソード【骨までおいしいお魚。やわらか一夜干しにしん/有限会社丸イ伊藤商店(余市町)】
2020年3月30日 公開

百年の伝統を有するにしん加工企業の挑戦

有限会社丸イ伊藤商店 代表取締役
伊藤正博さん
「弊社はにしんの一夜干しの製造を業務の柱としています。提供先は京都の老舗そば店で、鮮度や味はもちろん、丼に程良く収まるようサイズの詳細にまで厳しい規格が定められており、それらに丁寧に応えることで厳格なお客様とも信頼関係を構築してきました」
昭和の中期からにしん漁は長きに渡り不振が続きましたが、10年ほど前から前浜漁はV字回復。現在は年間2千トンが水揚げされるまでになっています。
「その一方、地元での消費は年々減少するばかりでした。小骨が多く食べづらい上に、〝みがき”くらいしか加工法がないことが最たる原因でした」
このままでは北海道の魚食の文化が衰退してしまう。そう考えた伊藤社長は公的研究機関の全面的な協力を仰ぎながら、にしんの加工食品の開発に乗り出します。
レトルト加工技術を深化させ新しいにしん加工の領域へ

塩、正油、キムチなど多彩な味がラインナップ。
「レトルトの魚商品は市販もされていましたが、細かく調査してみると『骨は軟らかいが身が硬い』『生臭さが残っている』『レンジ調理できない』など課題を抱えたものがほとんどで、この分野の研究はまだ過渡期ということもわかってきました」
とはいうものの、研究は試行錯誤の連続。
「通常の一夜干しでは魚の匂いが残ってしまう、骨を軟らかくしすぎると食味が落ちる、レトルトの時間が少し長いだけで皮がはがれてしまうなど問題は山積でした。過去のデータが乏しかったため、連日新しい試験や研究が続きました」
こうした取り組みの中から、対象魚を大豆の煮汁や豆腐製造後の上澄みに漬け込んでから一夜干しすると匂いが低減すること、レトルト処理の適温が115℃であることなどを一つひとつ突き止めていきます。さらに研究の領域は外見も。
「焼き目を残すための実験にも取り組みました。いくら味に自信があってもおいしそうに見えなければ誰も手を伸ばしませんから」
こうして研究を重ねること数年。平成29年に丸イ伊藤商店の長年の念願ともいえる「やわらか一夜干しにしん」が発表されたのです。
手軽でおいしくて食べやすい魚食文化の復活の兆しが
「当初は不安たっぷりでしたが、ふたを開けると評判は上々。『これなら子どもたちも喜んで食べる』という主婦の声やさらに介護施設の方などから『お年寄りにも骨を気にせず食べて頂ける』という声も届いています」
調理の手間がなく捨てるのはパッケージだけという手軽さも、何かと忙しい現代人にはピッタリ。軽くソテーしたりあるいはマリネにするなど一手間かけるとおいしさがアップするのも魅力だそう。
「ビジネスの側面だけではなく、魚を食べる文化に注目が集まったこともうれしいです。北海道の食卓に魚食をもう一度定着させるのが当面の夢ですね」
ここがこだわり!開発のポイント
最初のプロセスの塩漬けに「大豆の煮汁」「豆腐の上澄み」等の自然素材を添加することで、魚臭さを大幅に軽減しています。
身の食感や皮の焦げ目を損なうことなく、骨をやわらかく調理。味付けも程よく子どもやお年寄りでも食べられると大好評。
湯煎やレンジで温めるだけ。思いついたらすぐに食べられる手軽さも魅力。残るのはパッケージだけというエコもうれしい。
有限会社丸イ伊藤商店
北海道発!商品誕生エピソード
最新記事5件
商品開発の経緯や、お菓子作りへの思いを代表の柴田愛里沙さんに伺いました。
スパイスマニアでありながら、中学生のお子さんを育てるお母さんでもある小杉さんに、商品への熱い思いを伺いました。
固形物を食べることもままならない患者のために開発したチョコレートが「andew(アンジュ)」について、開発者の中村さんにお話を伺いました。
開発までの道のりや今後についてお話を伺いました
フライドチキンから生命の進化の歴史をたどるというユニークな講座を企画・指導している同館学芸員・志賀健司さんにお話を伺いました。
